前回の手塚治虫が無音の擬音「シーン」発明はウソについて、手塚治虫本人が自分が最初と云った出典をご教示いただきました。
手塚治虫『マンガの描き方』にこういう記述があります。
「音でない音」を描くこともある。音ひとつしない場面に「シーン」と書くのは、じつはなにをかくそうぼくが始めたものだ。
このほか、ものが消えるとき「フッ」と書いたり、顔をあからめるとき「ポーッ」と書いたり、木の葉がおちるときに「ヒラヒラ」と書くなど、文章から転用された効果は多い。 |
『マンガの描き方』は何十年も前に読んでいたのですが、すっかり忘れておりました。
そこだけ普通に読めば自分が「シーン」という言葉自体を発明したと云ってるようなじつに微妙な書き方がされていますな。「フッ」などは文章からの転用と明記されていますが、「シーン」は別になっていますから。
しかし、流れから考えて手塚さんとしては「シーン」という言葉自体を発明したわけではなく、それまで文章で使われていた「シーン」をマンガに初めて導入したと云っているんでしょう。
あたしはどうせ手塚さんのことだからまた適当な法螺を吹いてるんだろと想ってたんですが違っておりました。
この本の擬音の項目のひとつ前はオーバーなアクションについての話で、「目玉がとびだすほど高い」「おこって髪が逆立った」などの文章表現の「たとえ」をそのまま絵にしてしまうのがマンガだという説明をしています。
たんにオーバーなアクションをするのではなく、文章をあからさまにそのまんま絵にしてしまうというのはなかなかおもしろい着眼点で、あたしは結構感心しました。
マンガの擬音も文章表現の「たとえ」をそのまま絵にしてしまっているんであって、もともとの文章表現とはまったく違ったものになっています。
「シーンと静まりかえった」という文章はあくまで「目玉がとびだすほど高い」のような「たとえ」で、まあ分類すれば擬態語なんでしょう。それをあからさまにそのまんま絵にしてしまうことによって、またあからさまにそのまんま音にしてしまった。つまり擬音にしてしまったんですな。
やはり、手塚治虫が無音の擬音「シーン」発明はホントだったのです。
弟さんの回想によると、手塚さんは小学生時代、トイレに入ると「ヒュー」とか「ドカーン」とか毎回必ず擬音を発してたそうです。これは個室内の個人的いとなみの実況中継なんですかね。昔の汲み取り式だと、爆撃の効果音は臨場感があったでしょう。
なんせ、子供の時から絵やお話創りに長けていただけではなく、擬音の面でもすでに手塚治虫だったわけですから、これはほんとに天才ですな。
実際には手塚さん以前に無声映画の活弁士が「シーン」という言葉を擬音として使っていたような気もするんですが、裏が取れませんので手塚治虫が発明ということでいいでしょう。
ウェブ上を見て廻ると、石森章太郎が最初だという情報も結構流布しています。
あたしはガリガリの石森主義者なんですが、こんな話はこれまで聞いたことがありませんでした。しかし、なんせガリガリの原理主義者ですから、石ノ森のことはまったく関知しておらず、名前を変えてからそんな話をしたことがあるのかも知れません。
ただ、ウェブ上を見ただけの印象では、手塚治虫が「シーン」発明という書き込みがあるたびに、根拠も示さずいや手塚じゃなくて石森が最初という書き込みをする方がいて、どうもひとりの人が頑張ってこんな情報を広めようとしているような気がしないでもありません。
きちんとした根拠があるなら邪推ですいませんです。ご教示いただければ。
「吹風日記」は手塚治虫が「シーン」発明という部分に訂正を入れられたのですな。手塚云々はあの記事の本論とはあんまり関係がないし、せっかく名調子のいい文章の流れをぶった切ってまで説明を入れることもなかったと想うのですが。
しかも、平家物語の「森森として山深し」の森森は静寂の意味ではないのですよ。なんかこうなってくると小姑の重箱つつきみたいで我ながらどうかと想うし、しかも「すべからく」の話で記したように言葉というのは本来の意味とは違う使い方をする処に値打ちがあるので、あんまり言葉の間違い指摘みたいなことはしたくないのですが、さすがにこの流れではまずいので野暮を承知でひとくさり。
平家物語の伝本のうち高野本ではこの部分は「深々として山ふかし」となっていて、れいの全13巻のごっつい『日本国語大辞典』では静寂の意味に取っていますけど、これは少数派で、高野本を元にしている岩波書店『新日本古典大系』や小学館『日本古典文学全集』なんかは「深々」なのにわざわざ「これは森森の間違いで森が深い意味」というような註釈がついています。
ましてや、最初から「森森」の伝本ならこれはもうどうあっても静寂ではなく木が生い茂っているという意味ですな。
前回記したように森の字には静寂の意味は元々なく、静寂の意味で「森」を使うようになったのは漱石なんかの明治以降と書こうとして、念のため意味説明はともかく用例では物量作戦で一番頼りになる『日本国語大辞典』を引いてみると、「森々としてさおとない貌(かたち)ぞ」(拘幽操師説 18世紀初め)なんてのが静寂として出てくるではないの。
「さおと」というのは「小音」で、かすかな音さえないということですな。原文も確かめてみましたが、どう読んでも静寂の意味で「森々」を使っています。うーむ。
しかし、これは浅見絅斎の講義を弟子の若林強斎がノートに書き写したもんなんです。たぶん先生は「深々」と云ったのに生徒が「森々」と書き間違えたんでしょう。
やっぱり、言葉はこうやって間違えて使ってこそ豊かになるというものなんですよ。強斎さんが間違えてくれたおかげで、漱石や啄木は「森としている」という言葉を使えるようになったんですから。
このようにちょっと確かめた限りでは「シーン」というのは、「深々」が変形していって出てきたものみたいです。間違いだったらご教示をよろしく。
『マンガの描き方』の擬音の項目の最後に、手塚作品を英訳したときに「シーン」だけはお手上げになってしまったという話が出てきます。
「まさか、「SILENT」と訳すわけにもいかなかったろう」と手塚さんは書いてますけど、文章表現をそのまま使うのならそれが一番正しいはずではなかろうかと想います。日本のマンガの擬音ものちには「シーン」から発展していって、「しずか??」とか、「静寂!」みたいな、ますます文章表現そのままのあからさまなものになっていったわけですから。
じつは擬音ではなく、こういう文章表現そのままのあからさまという処に日本文化に隠されしすべての秘密を説き明かす秘鑰があったのだ!とここで論証すれば歴史に残る大発見になるやも知れませんが、いまのとこあんまり掘り下げて考えてないのでたんなる想い付きです。
<手塚治虫が無音の擬音「シーン」発明はウソ>を書いた時に、実際にはマンガに最初に導入したということなんだろうとは考えていたのですが、そのことにどれほどの意味があるのかあたしは疑問を抱いていました。
たとえば「ドッカーン」という擬音をいかにも爆発しているが如き形象で描くことはマンガ表現としてそれなりに意味があるんでしょうけど、「シーン」はそれほど形に凝れるわけでもないし、それまでにあった文章表現と何が違うのか。ことさら云い立てるほどのことなのか。
しかし、文章表現そのままのあからさまという処に着目すればいろいろ見えてくるというのは発見でした。
なにより、あたしにとって発見だったのは、なんだか肩書きだけに頼った通り一遍のつまらないテキストだと何十年前に一度読んで忘れていた手塚治虫『マンガの描き方』が、存外に深い考察を元にして考え抜かれた構成をほどされている本だということでした。
いや、これはほんとに驚いた。手塚治虫すごいな。
手塚治虫関連の絶望書店日記
○ブラック・ジャックの素
○ブラック・ジャックの素2
○神話を暴くとさらなる神話
○手塚治虫が無音の擬音「シーン」発明はウソ
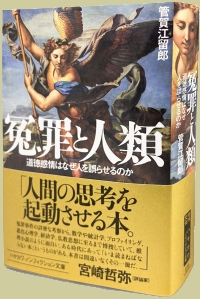
 絶望書店日記
絶望書店日記