このあいだBSで『十二人の怒れる男』をやっておりまして、久しぶりに観ました。
なんかこの話がおかしいという人々がいるみたいでして、あたくしも高校生の頃にテレビで観たときおかしいと想いましたけど、けどけどこの映画は陪審員制というか民主主義のおかしさ怖さを描いたもんなんでしょ?違うんスか?!!
現に起こっている殺人事件に対する善良な市民の目撃証言を机上の空論だけで次々と否定していくヘンリー・フォンダは終始悪魔的な表情を浮かべておりますし、とくに最後まで頑張っていた男が意見を翻すのはなんの理窟もなくただほかの十一人の数の圧力に屈しただけなんですから。
この最後の男に関してはいくらでももっともらしい理窟をくっつけることが可能なのに、あえてやってないのは、創り手側が「ひとりの煽動者によって民衆の意見なんていくらでも操作できるんですよ。有罪か無罪かなんてこんないい加減なもんなんです。民主主義なんてじつに怖いもんですね。数の力で正義なんてどうとでもなるんです」て訴えてるわけでしょ?違うんスか?!!
いや、これはガス人間の文章みたいなひねった視点ではなく、正統的な観方だと想ってたんですが。
あたしは映画や演劇の評論なんて一切読まないんですが、米国なんかではどんなような観られ方をしているのか、ご存じの方はご教示ください。なんか、ちと不安になってきた。
恐るべきデマゴーグであるヘンリー・フォンダが正義の人で、『十二人の怒れる男』が民主主義の正しさを描いた映画だと受けとめられているとするなら、身震いするほど怖いです。今頃こんなことを云ってるのは、あたしがなんかずれておりますか。
もちろんこれは裁判の話ですから通常の議論とは違ってちょっとでも疑いが差し挿めるのなら無罪でいいのですが、しかしそれにしたってあまりに無茶苦茶な論理で、証人の眼が悪い「可能性がある」(しかも、若く観られたいとか目立ちたいとかいう理由だけで偽証という重罪を犯している「可能性がある」!)ということで疑えるのなら証拠なんてすべてひっくり返すことができますし、「遠視かもしれない」「そんな創り話を信じろというのか」というじつにまっとうな反論は「サディストの偏見」としてヘンリー・フォンダにことごとく封殺されてしまう。
この映画自体がヘンリー・フォンダで、観客は陪審員というメタの図式があるわけですが、恐るべきデマゴーグの人心操作のトリックは最後の男にあるとあたしは視ます。
この男は自分の息子への憎しみのためから有罪(死刑)に固執するわけですが、無罪に転じるに当たって理窟がないだけではなくドラマもない。事件の読み解きや議論によって息子への憎悪が溶けるという展開があるわけではなく、ただ数の圧力によって自らの偏見を悔いるということになっている。
ここで容疑者が殺人を犯したかどうかということと、この男の偏見というまったく関係のない事象が意図的に混淆される。劇中でヘンリー・フォンダも使っている手口だ!ヘンリー・フォンダのほうはもっと悪質で、自分と違う意見は「偏見」と決めつけているわけですが。いや、創り手はさらに上手で「自分」ではなく「ヘンリー・フォンダ」と違う意見は「偏見」と決めつけているわけですが。
作劇としてもおかしな具合で、憎んでいるはずの息子の写真を大事に持っていて、赦したときにその写真を引き裂いて捨ててしまうというちぐはぐな話になっている。
これはまあ、子離れできない親が代償行為としてほかの子供を死刑にしようするんであって、最後は逆に容疑者ではなく息子の写真を捨てることによって子離れすると読み解くこともできるのですが、そんな複雑に交叉した図式を当てはめるには肝心の逆転時にさえドラマがない掘り下げ不足の展開ではやはり無理があって、息子と容疑者に対する憎悪と赦しは単純に連動しているべきなんですが。実際、ほとんどの観客は連動させて観ているはずで、写真を破るという劇的な幕切れになんとなく誤魔化されているだけです。
これだけ出鱈目な話が論理的な話であるという印象さえ抱かせながら観客の胸を打つのはヘンリー・フォンダの説得術と同じくテクニックとしては最上で映画としては大成功、あたくしとしても傑作として認むるに異論はないわけですが、人々がそのまま「正義」として受け取っているとするならば。
自分たちと違った国の考え方を「サディストの偏見」であると、アメリカ人はディベート・テクニックではなく本気で信じ込んでいるようで、そんな米国の独善性を非難する人々もこの映画は「正義」として受け取っているとするならば。
いや、人々がこんな簡単に操られるわけではなく、たんなるあたしの想い過ごしならそれでいいのですが。なんか、ちと不安。論理的な映画だと考えてる人はほんとにいるようで、そういう方に限って論理的思考の大切さを説いてたりして、あたしにはとても信じられんのですが。
文明の衝突がどうしたとか、あるいは掲示板文化がどうとかいう以前に、こういう基本的なことをはっきりしておいてもらわんと、どうにも落ち着かんな。
英語に弱いせいか、タイトルの意味がもひとつよく判らんということもあるし。こういう怖さを顕した題名と考えるのはさすがに深読みか。聖書か何かの言葉でしたっけ?イエスが逮捕されて理性を失った十二使徒のことだったような気がするけど、違ったかな?
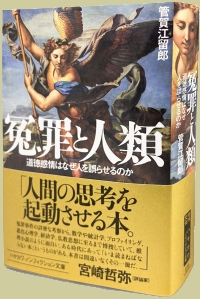
 絶望書店日記
絶望書店日記